株式会社GENDA(以下、GENDA社)が、武蔵小山にあるゲームセンター「GameGoose武蔵小山店」を運営する株式会社ゲームグース(以下、ゲームグース社)の発行済株式を100%取得し、子会社化しました。買収金額は非公開ですが、同社が積極的なM&A戦略を進めている事実は市場から高く評価され、株価上昇にも寄与しています。

1. GENDA社の概要とM&Aの実績
1.1 GENDA社の基本情報
社名:株式会社GENDA
本社所在地:東京都港区
GENDA社は、もともとアミューズメント事業を中心に成長を遂げてきた企業ですが、その後、他社買収による事業拡大を積極的に行い、企業価値を高めてきたことで知られています。SHIFT社とともに「現在のM&Aブームのきっかけ」とも称される企業群の一角に位置づけられており、IPO前に11件、IPO後も含めると合計40件におよぶM&Aを行ってきました。このように、アミューズメント業界では国内有数の積極的バイヤー(買い手)として注目されています。
1.2 市場からの高評価と株価急上昇
同社の積極的なM&A戦略は、単に資金力や案件数の豊富さだけではなく、「買収後の事業再生手法」に強みを持ち、実際に業績を伸ばしている点が市場から評価されています。通常、買収を行う企業は、その後のシナジー創出や業績改善が不確定要素を多く含むため、市場から慎重に見られがちです。しかしGENDA社の場合、買収先企業の運営ノウハウやDX化支援を通じて目覚ましい成果を上げてきた事例が多々あり、それが投資家の信頼を勝ち取っている大きな要因といえます。

2. ゲームグース社の買収概要
2.1 買収対象会社:株式会社ゲームグース
社名:株式会社ゲームグース
所在地:東京都品川区小山
運営店舗:「GameGoose武蔵小山店」1店舗
武蔵小山駅周辺は、一日あたりの乗車数が約5万人と、首都圏の中では比較的落ち着いた駅の規模ながら、昔ながらの商店街や地元密着の店舗が並ぶ非常に活気あるエリアです。ゲームグース社の運営する「GameGoose武蔵小山店」は、いわゆる“古き良きゲームセンター”の雰囲気を残し、地域コミュニティにも一定の認知と根強いファン層を持つと想像させます。
以下は店舗概要

2.2 決算公告から読み解く財務状況
公表されている情報によれば、ゲームグース社は2021年(約4年前)の決算公告しか確認できません。その内容から察するに、債務超過・赤字で推移していた可能性が高く、経営状態はかなり厳しかったと推測されます。また、従業員数(被保険者数)は8名ほどであり、組織規模の小さい事業者であることがわかります。ゲームセンターはコロナ禍で特に打撃を受けた業界の一つであり、売上減少と固定費負担が重なった結果、財務上の苦境に立たされた例は少なくありません。


一方、こうした財務状態の企業は、買い手にとって「再生余地がある」と判断されれば投資妙味もありますが、同時に債務超過の解消方法や、財務体質改善のロードマップをどう描くかが大きな課題となります。GENDA社は、過去のM&Aのトラックレコードから、同様の状況にある企業を買収後、売上を2倍以上伸ばした実例があるとされています。これまでの実績とノウハウを活用することで、ゲームグース社の経営状態をどのように改善していくのか注目されます。

2.3 買収金額の非公開
今回の株式取得にかかる買収金額は公表されていません。非上場企業のM&Aではよくあることですが、市場関係者にとっては具体的な評価額を推測しにくい点は一つの興味深い要素といえます。債務超過企業を買収する際には、たとえば「負債の引き受け条件」「今後の追加融資(あるいは債務のリスケジュール)」「新株発行による資本注入」など、複合的な金融スキームが採用されることも少なくありません。買収金額がゼロあるいはマイナスになる(いわゆるネガティブプライスM&A)ケースも、業種や財務状況によっては十分あり得ます。
3. GENDA社のM&A戦略と再生ノウハウ
3.1 DXを中心とした事業再生のアプローチ
GENDA社が積極的に取り入れているのは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の手法です。アミューズメント施設の運営には、従来コインや紙幣を使用してゲームをプレイする仕組みが定着しており、両替機の維持管理など運営コストが大きくかかるうえ、利用者側にも心理的負担がありました。しかし、DXを活用することで、以下のような課題解決が期待できます。

決済アプリの導入
ユーザーが自身のスマートフォンで簡単に課金できるアプリを利用すれば、両替の手間が不要となり、利用意欲が向上する可能性が高まります。現金を持ち歩かないライフスタイルが一般化しつつある現代において、クレジットカード・電子マネー・QRコード決済など、キャッシュレス対応はビジネスの必須要素となってきています。
オペレーションの省人化
DX化によって、キャッシュハンドリング業務や集計作業が不要に近づきます。これにより、限られた人員でもスムーズに店舗運営ができるようになり、人手不足や労務管理上のリスクを低減する効果が期待できます。
顧客データの活用
デジタル決済を導入すると、ユーザーの利用履歴や嗜好をデータとして蓄積できます。これをもとに、イベント企画や景品設定など、よりきめ細かいマーケティング施策が可能になります。加えて、ユーザーとのコミュニケーション手段としてのアプリ活用も進めれば、LTV(ライフタイムバリュー)の向上が図れるでしょう。
3.2 旧来の産業を買収してDXで蘇らせる「型」
近年、旧来型の産業を丸ごとM&Aで買収し、DXで付加価値を高めて事業再生や効率化を図る手法は幅広い業界で注目されています。日本では少子化が深刻化しており、特に労働集約的な産業では後継者不足や人手不足が深刻化しています。そうした課題に対し、デジタル技術の導入による“生産性向上”をキーワードに、積極的に古い体質の企業を買収していく動きが増えているのです。
DXはさまざまな産業でゲームチェンジャーとなり得る要素があります。アミューズメント施設も例外ではなく、キャッシュレス決済やオンラインによる顧客囲い込みは将来の主流になりつつあります
4. 今後のアミューズメント業界とDXの展望
ゲームセンター業界は、一時期「斜陽産業」とも言われ、近年ではスマホゲームやオンラインゲームとの競合が激化しています。しかし、リアル店舗での体験価値を提供できるゲームセンターは根強いファンが多く、さらに最新のデジタル技術との融合が進むことで新たな可能性が見込まれます。例えば、VR/AR技術を取り入れた新感覚のアトラクションや、eスポーツの大会会場としての活用など、多様な形で盛り上がりを見せています。
DXの観点からは、リアル店舗の活性化をオンラインと掛け合わせることで、ファンコミュニティを拡大し、地方創生につなげる動きも出始めています。GENDA社のように、旧来型の施設を買収し、最新のデジタル技術で再構築するケースは、今後も増える可能性が高いでしょう。
5. まとめと展望
今回のGENDA社によるゲームグース社の子会社化は、アミューズメント業界のM&A動向を示す一つの好例といえます。買収先企業が債務超過や赤字経営であったとしても、買い手側が明確なDX化戦略や再生ノウハウを持っていれば、十分に再起を図り、事業を大きく成長させる余地が残されています。少子化やコロナ禍後の消費行動変化といった厳しい外部環境の中であっても、新たな付加価値を提供できる形に進化すれば、企業価値を高めることが可能です。
また、M&Aの成否を分けるのは「買収価格の交渉」だけではなく、「買収後のPMI(Post Merger Integration=買収後統合)」における具体的な実行力と綿密な計画です。DXやAIといった先端技術を積極的に取り入れ、オペレーション効率化やサービス内容のアップデートを着実に進めていけば、企業としての競争力は確実に高まっていくでしょう。
アミューズメント業界に限らず、旧来のビジネスモデルが時代に合わなくなった企業がDXを取り入れて再生する事例はますます増えていくと考えられます。M&Aアドバイザーの立場からは、こうした「企業再生×DX」というアプローチが有効なケースを的確に見極め、財務・法務・労務のリスクをコントロールしながら、買い手・売り手双方の利益にかなう形で交渉を進めることが肝要となります。
本記事が、M&Aを考えている経営者や投資家の方、もしくはアミューズメント業界に興味を持つ皆様にとって、何らかの示唆を与えるものであれば幸いです。これからも多くの企業が果敢にM&Aを活用し、日本の産業構造を変革していく流れは続くでしょう。その際、財務・法務の基盤をしっかりと固めながらDXやAI技術を巧みに導入し、新しい市場価値を生み出すことが、企業成長の大きな鍵となるはずです。
プライマリーアドバイザリー株式会社
代表取締役 内野 哲


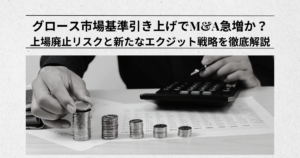

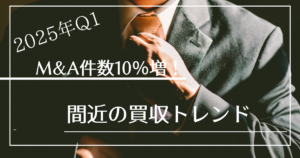





コメント