1.2024年に相次いだ中小企業M&A仲介業の不正発覚
少子高齢化が進む日本では、中小企業オーナーの高齢化に伴い後継者不足が深刻化しています。その打開策の一つとして、近年は小規模から中堅企業間のM&A(企業の買収・合併)が活発化してきました。事業承継を目的としたM&A取引は年々増加傾向にあり、取引の仲介に携わる企業も多様化しています。
しかし、2024年には中小企業M&A仲介業界における不正行為が複数明るみに出て、拡大する市場のリスクが改めて浮き彫りになりました。報道によれば、不正の主な例は以下のとおりです。
- 統合契約時の不適切な情報開示
- 仲介手数料を優先するあまり、事実を隠蔽したり取引を急かす営業活動
- 成功報酬重視の給与体系が誘発した利益至上主義
これらは単なる「一部社員のモラル欠如」にとどまらず、仲介会社のガバナンスや内部統制の不備という構造的課題を示唆しています。特に高率の成果報酬制度は、不正を助長する恐れが大きいと専門家から警鐘が鳴らされています。
2.業界をリードする仲介会社が槍玉に上がる理由
2-1. 過度なプレッシャーと高額インセンティブ
大手のM&A仲介企業には、インセンティブ比率が40%を超え、年収が数千万円に達する社員が存在する場合があります。高額な成果報酬は優秀な人材を呼び込み、営業を活性化させる利点がある一方、「結果を出さなければ高額報酬は得られない」という強いプレッシャーをもたらします。
その結果、一部の社員は「多少のグレーゾーンでも成約を優先したい」という思考に陥りやすくなり、不正を実行してしまうリスクが高まるのです。また、一度不正が通用してしまうと、「会社も黙認しているのでは」「さらに利益を得られるかもしれない」という認識が広がり、モラルや法令遵守への意識が希薄化しやすいのが実情です。
2-2. 社員個人のモラルだけでは防げない組織的課題
不正を「一部社員の逸脱行為」と断じるのは危険です。企業風土やリスク管理の甘さなど、組織的問題が背景にあるケースが多いからです。具体的には次のような課題が指摘されています。
- 企業文化の問題
数字至上主義が蔓延し、「成約件数や手数料収入の最大化」が最優先されがち。 - ガバナンス不全
不正を報告しても、業績への影響を恐れる上層部が隠蔽を図ったり、告発を軽視する場合がある。 - 内部統制の甘さ
コンプライアンス研修が形骸化し、内部通報制度も形だけで機能不全。通報者への報復リスクが根強く、不正が放置されやすい。
これらの問題が明るみに出ると、社会的影響は業界を代表する企業ほど甚大です。不正発覚により企業価値が毀損するだけでなく、業界全体の信用低下にも大きく寄与してしまいます。
3.不正が業界にもたらす影響と不信感の拡大
3-1. 取引相手・顧客との関係悪化
M&Aでは、買い手と売り手の双方が納得して合意に至ることが理想です。しかし、不正の実態が表面化すると、以下のような疑念が生じ、取引が停滞・複雑化する恐れがあります。
- 「開示されている情報は正しいのか」
- 「仲介手数料を稼ぐために、取引を過度に急かされていないか」
その結果、買い手・売り手ともに精度の高いデューデリジェンス(企業調査)を行う必要に迫られ、交渉期間は長期化し、コストも膨張します。さらに、不正の事例が報道などで大きく取り上げられるほど、より大手や上場企業との取引を選好する動きが強まり、中小企業間のM&Aは敬遠されやすくなるでしょう。
3-2. 業界全体の信用失墜
一部の企業での不正であっても、多くの人々は「M&A仲介業界全体が怪しい」と認識してしまいがちです。特にオーナー経営者にとってM&Aは、自社と従業員の将来を左右する重大事項です。不信感が蔓延すると市場全体が萎縮し、仲介業者のみならず、M&Aアドバイザリーや金融機関の信用にも悪影響が及ぶ可能性があります。その結果、事業承継や企業連携が滞り、日本経済にとっても痛手となります。
4.不正が起きる原因を深掘りする
4-1. 過度な成果主義とコンプライアンス意識の欠如
インセンティブ比率が極端に高い成果主義の下では、社員が短期的利益の追求に集中しがちです。本来、仲介会社は買い手と売り手双方の「長期的な企業価値向上」を支援する役割を担うべきですが、利益偏重の企業文化ではその使命が歪められます。さらに、法令遵守や倫理観の教育が不足すると、現場レベルでの判断ミスや意図的な不正を招きやすくなります。
4-2. 内部統制・ガバナンス体制の不備
不正を防ぐためには、以下のような実効性あるガバナンス体制が不可欠です。
- 内部通報制度(ホットライン)の整備
匿名通報や通報者保護の仕組みを確立し、現場の声を経営陣が把握できる体制を作る。 - 第三者監査の導入
外部専門家や監査法人によるコンプライアンス監査で、定期的にリスクを点検する。 - 経営層のコミットメント
トップマネジメントがコンプライアンスを最優先事項として明確に打ち出し、全社的に意識を共有させる。
急拡大した仲介会社では、営業面での成長速度にガバナンス整備が追いついていない事例が散見されます。通報者が処分の対象になるような組織風土では、違反行為を見過ごす温床が生まれ、やがて不正が常態化してしまいます。
4-3. 業界特有の情報非対称性
M&A仲介においては、売り手・買い手・仲介会社それぞれが保有する情報量に格差があります。特に中小企業のオーナー経営者は、専門知識や情報源が限られているため、仲介会社に依存しがちです。仲介側が情報を囲い込み、契約を急かすなど不十分な説明のまま取引を進めると、後に深刻なトラブルに発展する可能性が高いでしょう。
5.業界が目指すべき方向性:ガバナンス強化と誠実な情報開示
5-1. インセンティブ制度の見直し
- 過度な歩合制の排除
極端な報酬比率が社員を不正に走らせるリスクを高めるため、固定給とのバランスを適正化する。 - 長期的成果指標の導入
成約直後の売上だけでなく、1年後・3年後の顧客満足度や企業成長度を評価対象に含める。 - 企業価値・従業員満足度の重視
短期的な数字のみならず、持続的な企業価値向上や関係者との良好な連携を成果指標とする。
こうした仕組みにより、社員が目先の利益に走る動機を抑制し、健全なM&A仲介を促進できます。
5-2. 情報の透明化と適切なデューデリジェンス
- 契約書の重要条項の丁寧な説明
表明保証条項や違約金、競業避止義務などの法的リスクを、専門家と連携してわかりやすく解説する。 - 情報の一元管理と共有
オンラインプラットフォームなどを活用し、全当事者が常に同じ情報にアクセスできる環境を整備する。 - 第三者のチェック体制
仲介会社が恣意的に情報を操作しないよう、外部のアドバイザーや監査法人による検証プロセスを導入する。
これらを徹底することで、隠蔽工作や情報操作を防ぎ、公正で信頼性の高いM&A取引を実現できます。
6.最も重要なこと:倫理観を重視した企業体質の確立
今回問題となった不正行為は、中小企業だけではなく、研修制度や管理体制が充実しているはずの大手仲介会社でも相次ぎました。売上至上主義や成長優先のあまり、倫理面の軽視が社内に深く根付いていた可能性があります。
古代ギリシャの医師ヒポクラテスの誓いにある“Primum non nocere(まず害をなさない)”という言葉は、あらゆる専門職の基本姿勢ともいえます。医師が患者の利益を無視して不必要な治療を行えば生命にかかわるのと同様、M&A仲介においても、企業と従業員の未来を左右する重大な責任があります。
「顧客に不利な情報を知っていながら、自社の利益を優先する」のは、専門家としての使命を自ら否定する行為です。業界全体で改めてこの倫理観を再確認し、組織文化とガバナンスの両面から改革を進めることが急務といえます。
7.まとめと今後の展望
2024年に表面化した中小企業M&A仲介業界の不正は、成果報酬制度やガバナンス体制の甘さ、情報非対称性といった構造的な課題を浮き彫りにしました。一方で、中小企業の事業承継や成長戦略としてのM&A需要は今後も高まる見込みです。したがって、業界の健全化は日本経済全体にとっても重要なテーマとなります。
- 社員・企業レベル
成果主義の見直しやコンプライアンス教育の強化、内部通報制度の整備など、ガバナンスの実効性を高める。 - 業界・行政レベル
自主規制ルールやM&Aガイドラインを徹底し、情報弱者となりがちな中小企業オーナーを保護するための制度を検討する。 - 経営者サイド
複数の仲介会社や専門家を比較し、取引後のPMI(統合プロセス)も視野に入れた長期的なM&A戦略を構築する。
これらの対策を進めることで、売り手・買い手が安心して成約できる市場が育ち、中小企業がさらなる活力を得ることが期待されます。
8.おわりに:信頼できるパートナーを見極めるために
不正が表沙汰になると、M&A仲介業界だけでなく、M&A自体への不信感も広がりかねません。しかし、正しく情報開示を行い、公正に仲介を行う専門家と組めば、M&Aは中小企業にとって大きな飛躍のチャンスです。信頼できるパートナーを選ぶには、以下のポイントを押さえると良いでしょう。
- 複数の仲介会社や専門家に相談する
報酬体系や提案内容、担当者の誠実性を多角的に比較・検討する。 - 疑問点や不安は早期に明確化
契約書の条項や費用の内訳で不明点があれば、弁護士・公認会計士・税理士といった専門家のセカンドオピニオンを活用する。 - 契約書・報酬体系・PMI支援の確認
自社に不利な契約条件が含まれていないか、必要に応じて修正交渉を行う。
上記を徹底するだけでも、不正やトラブルのリスクは大幅に低減します。もしM&Aを具体的に検討している方や、将来的に事業承継で悩まれている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士・M&Aアドバイザーとして、法的に正確かつ論理的なサポートで、安全・安心なM&Aの実現を全力でお手伝いいたします。
プライマリーアドバイザリー株式会社
代表取締役 内野 哲
プライマリーアドバイザリー株式会社経済産業省中小企業庁 M&A支援機関登録制度・M&A仲介・M&Aアドバイザリーのプライマリーアドバwww.primary.co.jp
本稿は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の法律相談・税務相談に代わるものではありません。実際の検討にあたっては、必ず弁護士や公認会計士・税理士などの専門家にご相談ください。




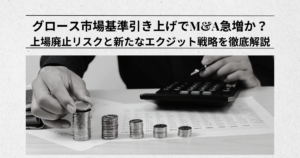

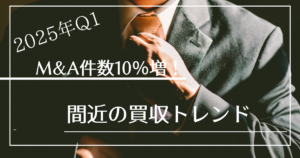



コメント