2025年4月2日、東京証券取引所がグロース市場における上場維持基準の引き上げを検討中である旨が報じられました。NHKの報道によれば、スタートアップ企業やベンチャー企業が主に上場するグロース市場において、引き上げ後の基準を満たせない企業は上場廃止の可能性があるとのことです。
東証 スタートアップなどグロース市場 上場維持基準引き上げへ

この新基準は、現在グロース市場に上場している約612社のうち、時価総額100億円未満の約429社(全体の7割弱)に影響を及ぼすと推測されています。実際にこれらの企業が基準をクリアできなければ、上場廃止となるおそれがあります。しかも、今後新たに上場を目指すスタートアップ企業も上場要件を満たすことが難しくなり、結果として「IPO(新規株式公開)」という選択肢が遠のく可能性が高まります。
この背景を踏まえ、多くのスタートアップが「M&A(合併・買収)」に活路を求めると予想されます。資金調達やエクジット(投資回収)手段として、これまで主流とされていたIPOのハードルが上がることにより、今後はM&Aラッシュが起こるだろうとの見方が急速に広がっています。本記事では、財務・法務、そしてDX・AIにも精通したM&Aアドバイザーの視点から、上場維持基準引き上げによる影響とM&A戦略の有用性について、知的かつ分かりやすく解説いたします。
1.グロース市場の上場維持基準の背景
東京証券取引所が設立したグロース市場は、成長性の高いベンチャー企業が上場しやすいよう設計された市場区分でした。通常のプライム市場(旧・東証一部)やスタンダード市場(旧・東証二部、JASDAQ・マザーズの一部を再編)に比べて柔軟な基準で上場できるため、スタートアップが積極的に利用してきた経緯があります。
今回の引き上げが実現すれば、時価総額や純資産などの要件が厳格化され、現行では上場を維持できている会社でも新基準を満たせずに上場廃止となるケースが出てくる可能性があります。さらに、今後IPOを目指す企業も、時価総額のハードルがこれまで以上に高くなることで、上場審査を通過しにくくなってしまうでしょう。
2.新基準下で想定される企業の動き
1)上場企業の戦略再考
現時点でグロース市場に上場している企業が、新基準を満たせない場合の選択肢としては以下のようなものが考えられます。
- 追加の資金調達や業績拡大による時価総額の向上
さらなる成長戦略を急ぎ、投資家からの追加出資や社債発行などによって資金を調達し、事業拡大に挑むことで時価総額を引き上げる方法です。もっとも、短期的に実行するには高い経営能力が求められるうえ、市況の変動が激しい場合にはリスクも大きくなります。
- M&Aによる事業売却や経営統合
より大きな企業グループに参画することで、安定的に事業を継続しつつ、株主へリターンを提供する道を探ることも有力です。上場廃止のリスクを避けるためには、早期の決断が求められるケースもあるでしょう。
2)上場を目指していたスタートアップの動き
近い将来でIPOを計画していたスタートアップにとっては、時価総額の要件が引き上げられることにより、「従来以上に大規模な資金調達や事業拡大をクリアしないと上場が難しくなる」という状況になります。結果、IPOを断念せざるを得ない企業や、上場時期を大幅に延期せざるを得ない企業も出てくるでしょう。
そのため、こうしたスタートアップが投資家・創業者へのリターンを確保するための手段として、M&Aがさらに注目されることが予想されます。特にエクジットを焦るベンチャーキャピタル(VC)や投資家が存在する場合、M&Aによる売却は現実的な選択肢と言えるでしょう。
3.IPOのメリットとジレンマ
IPO(新規株式公開)は、会社を大きく飛躍させる象徴的なイベントであり、創業者や投資家にとって大きなリターンを得られる場でもあります。また、IPOを目標とすることで企業のガバナンス体制が向上し、人材の獲得や社会的信用の向上にもつながります。
一方で、報道でも指摘されているとおり、時価総額が低いままIPOを果たした場合、実際の調達資金が限定的となってしまうジレンマがあります。たとえば時価総額50億円程度での上場だと調達額は10億円程度になるとされ、監査・ガバナンス維持コストや監査法人への報酬支出など、上場企業としてのランニングコストを吸収しきれない可能性が出てきます。その結果、強みを伸ばすための先行投資に回せる資金が不足し、非上場の強豪他社に後れを取るリスクが高まってしまうのです。
さらに、多くの創業者がIPO後、株式を売却したいと考えていても、ロックアップ期間(一定期間の株式売却が制限される)や取締役としての継続在任が条件づけられ、十分にキャッシュ化しにくいのが現状です。そこで「証券ローン」という手法で間接的に資金を手にするケースもありますが、融資コストやリスクが伴います。
4.M&Aがもたらす新たなエクジット機会
こうした背景のなか、M&A(合併・買収)はIPOに匹敵するエクジット手段として注目されています。特に以下の点がIPOに比べて魅力的と言えます。
1)即時のキャッシュ化が可能
M&Aの場合、売却金額が一括または複数回にわたって支払われる契約形態が一般的です。そのため、創業者や株主は取得した資金を元手に、再投資や個人の資産形成に充てることができます。証券ローンを組む必要もないため、リスクを極小化できるメリットがあります。
2)成功確率の高さ
IPOは取引証券所や投資家からの評価次第では、上場審査に通過できないリスクが常につきまといます。一方M&Aの場合は、一定の営業利益(たとえば3億円超)を確保できている企業であれば買い手が比較的見つかりやすいとされます。加えて、近年は国内外の大企業だけでなく、プライベートエクイティファンドや事業会社の買収意欲が高まっており、売り手市場とも言える環境が整いつつあります。
3)ガバナンス体制や株主構成の柔軟さ
IPO後は株式市場からの監視が厳しくなる一方で、M&Aでは買収側の企業文化やガバナンス体制を生かしながら合流する形となるため、IPOに比べて柔軟な組織運営が可能です。必ずしも大掛かりなコーポレートガバナンス改革が求められるわけではなく、買収先の企業の体制や監督を活用しつつ、成長に邁進できます。
5.国内の起業件数増加とスタートアップ・M&Aの展望
日本においては近年、政府がスタートアップ支援の強化を掲げるなど、起業家を増やす取り組みが進められてきました。その主要なインセンティブとして期待されていたのがIPOですが、上場基準引き上げにより、その選択肢が狭まることになります。一方で、経営者や投資家にとって魅力的な出口となるM&Aの選択肢が確立されれば、リスクを取りやすい土壌が生まれ、結果として国内の起業件数が増加する可能性があります。
実際、米国ではスタートアップが一定規模になると、大企業やプライベートエクイティファンドに買収されるケースが少なくありません。創業者は得た資金で新たなビジネスを立ち上げたり、投資家としてエンジェル投資に回ったりと、スタートアップエコシステムが循環する良循環が生まれています。日本でも、IPOだけに頼らずM&Aを積極的に活用する流れが広まれば、同様のエコシステム拡大が期待できるでしょう。
6.まとめと今後の展望
東京証券取引所によるグロース市場の上場維持基準引き上げは、多くのスタートアップにとってIPOのハードルを高める一方、M&Aを利用したエクジットや事業拡大の可能性を再考させる大きなきっかけとなるでしょう。特に時価総額100億円未満で上場している企業にとっては、上場維持と事業成長のバランスをどう取るかが緊迫した課題となります。将来的には、日本のスタートアップエコシステムがより一層発展し、IPOだけでなくM&Aによるエクジットも当たり前となる時代が訪れるでしょう。上場市場の改革が加速するこのタイミングでこそ、柔軟な選択肢を念頭に置き、企業・投資家・アドバイザーが連携を深めることが求められています。そうした連携の中でこそ、新興企業によるイノベーションが促進され、日本経済全体の競争力強化につながるのではないでしょうか。
プライマリーアドバイザリー株式会社
代表取締役 内野 哲
(本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としたものであり、いかなる投資判断や法的行為も保証するものではありません。実際の手続きや契約にあたっては、必ず各分野の専門家にご相談ください。)
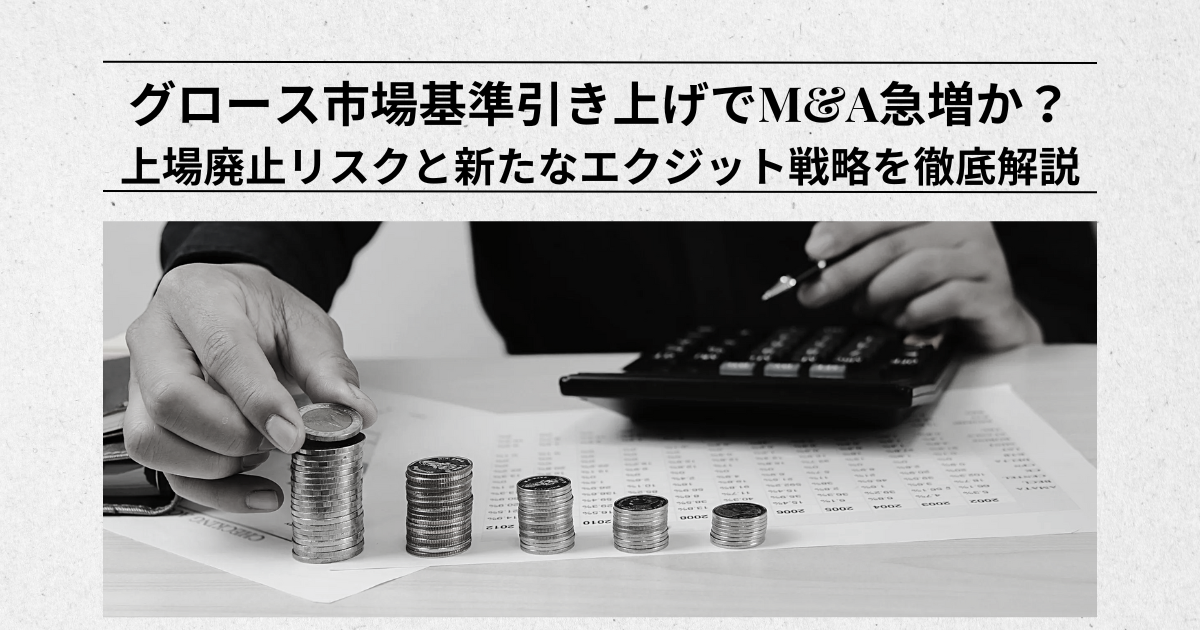


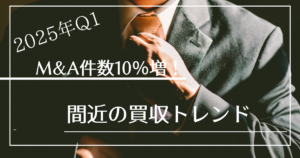






コメント