Bain & Company の「This Time It’s Different: The Strategic Imperative in Private Equity(on March 03, 2025)」という記事の内容を、日本の読者にも分かりやすい表現に翻訳・解説したものです。以下、記事の主要なポイントごとにセクションを分け、背景や今後の展望について解説しています。
はじめに:今度は違う―プライベート・エクイティ業界の新たな戦略的挑戦
原文タイトル:
This Time It’s Different: The Strategic Imperative in Private Equity
翻訳・解説:
プライベート・エクイティ(PE)業界は、40年前に創業者主導でレバレッジド・バイアウトを実施する小規模な集団として始まりました。当時の戦略は、次のディールを探し出し、レバレッジ(借入金)を最大化することに集中していました。しかし、世界金融危機やその後の市場回復を経て、業界は「単なるディールメイキング」から、より戦略的な経営と組織能力の強化へと変化してきました。
【要点】記事の主要メッセージ
- 戦略の重要性の再認識
- かつては多くのPEファームにおいて戦略は表面的なものだったが、今後の競争環境では、戦略が中心的な役割を果たす必要がある。
- 業界構造の変化
- マクロ経済環境の変化(低金利政策の終焉、金利上昇、資本流入の変化)や、資産評価の変動などにより、今後10年間でこれまでと大きく違った局面が訪れる。
- 競争環境の激化
- ディールの獲得、資本調達、そして有能な人材の確保といった面で、従来のやり方だけでは太刀打ちできない環境になっている。
セクション1:過去から見るPE業界の進化
原文の趣旨:
- 初期は、次の買収案件を探すこととレバレッジの最大化が主な戦略であった。
- 世界金融危機を経て、リターンを安定的に出すための明確で再現可能なモデルが求められるようになった。
- その後、金利が低く経済成長が続いたことで、単に「波に乗る」だけのディールメイキングが通用した。
日本語訳・解説:
プライベート・エクイティ業界は、かつては「次の案件をいかに早く手に入れるか」という単純な競争で戦っていました。しかし、2008年の金融危機以降、単なるファイナンス技法に頼るだけでなく、再現性のあるリターンモデルの構築が急務となりました。そして、低金利と経済成長に支えられた市場環境では、多くのファンドが単に市場の勢いに乗る戦略を採用していました。しかし、今後はその「波乗り戦略」では通用せず、各社が独自の戦略を明確に描き、実行に移す必要があるのです。
セクション2:マージン圧迫とフィー構造の変化
原文の趣旨:
- 伝統的な「2 and 20」フィー(運用手数料2%、成功報酬20%)モデルに対して、近年は競争激化によりフィーの引き下げ圧力がかかっている。
- 資本獲得の競争が激しくなると、自然とフィーの値引きが進み、コインベストメント(共同投資)の動きも加速するため、収益構造に大きな変化が生じている。
日本語訳・解説:
現在のPE市場では、従来の「2 and 20」モデルに基づく収益構造が、競争激化の影響で大きなプレッシャーを受けています。つまり、ファンドが獲得する運用手数料は金融危機以降、半分近くにまで低下しているとの分析があります。さらに、パブリック市場とプライベート市場の融合が進む中、従来の高額フィーを支えられなくなる可能性も指摘されています。たとえば、VanguardやFranklin Templetonなどの大手ウェルスマネージャーが、個人投資家向けに低コストで代替投資商品を提供し始めており、これがPE業界にも影響を与えています。
セクション3:資金調達環境の変化
原文の趣旨:
- 現在、PEファンドの資金調達環境は厳しい状況にある。
- しかし、ディールの回復とともに一定の改善が期待されるものの、資金は「持っている者」と「持たざる者」との間で格差が広がる傾向にある。
- 資金調達では、従来の「ランチと握手」的なアプローチではなく、B2Bのプロフェッショナルな投資家対応が求められている。
日本語訳・解説:
資金調達面では、依然として厳しい環境が続いています。特に、既存の大手や実績のあるファンドに資金が集中する傾向が強く、新規参入や小規模なファンドは苦戦を強いられる可能性が高いです。また、個人投資家や国家系ファンド(ソブリン・ウェルス・ファンド)の存在が大きくなり、従来の大口機関投資家だけに依存するモデルから脱却する必要が出てきました。こうした中で、ファンドは高度なIR(投資家向け広報)体制を整え、しっかりとした価値提案を示すことが求められています。
セクション4:資本提供者の多様化―個人投資家とソブリン・ウェルス・ファンドの台頭
原文の趣旨:
- 個人投資家が全世界の資本の約50%を保有しているにもかかわらず、代替投資ファンドにおける資産運用額はわずか16%に留まっている。
- 今後、個人投資家向けや半流動性のある商品を通じ、これらの資金を取り込む戦いが激しくなる。
- 同時に、ソブリン・ウェルス・ファンド(SWF)の規模も拡大しており、これらの資金提供者とのパートナーシップが業界の資金流入の鍵となる。
日本語訳・解説:
今後の資金調達の大きな源泉として、個人投資家や国の資金(ソブリン・ウェルス・ファンド)の存在が浮上しています。個人投資家は世界の資本の半分を保有している一方で、従来は代替投資ファンドに十分な割合で組み入れられていませんでした。しかし、流動性の高い半流動性商品などを通じて、個人投資家向けの商品の提供が進むにつれ、今後この割合が大きく変化する可能性があります。また、SWFは今後も年率11%で成長し、総額が17兆ドルに達すると予想されています。こうした巨額の資金を背景に、大手ファンドとのパートナーシップや共同投資の重要性が増していくでしょう。
セクション5:規模の重要性の高まり
原文の趣旨:
- これまで、小規模なファンドでも十分な実績を上げることができたが、今後は規模の経済がより重視される局面に入る。
- 大手ファンドは、資金調達、ディール獲得、そして投資先企業のパフォーマンス向上において、有利な立場を取るようになる。
日本語訳・解説:
従来は規模に関わらず良く運営されているファンドならば十分な成功を収めることが可能でした。しかし、今後は競争が激化する中で、規模の大きさ自体が大きな武器となります。大規模なファンドは、資本調達力やディールの質、そして投資先企業への積極的な支援体制を整えやすいため、相対的に有利な立場を占めるようになると予想されます。
結論:今後のPE業界で勝ち抜くために
この記事全体を通して、以下のポイントが強調されています。
- 戦略の転換が必須: 今後の厳しい環境下では、単なるディールメイキングではなく、明確な戦略と実行力が成功の鍵となる。
- 収益構造の変化への対応: 手数料圧迫やフィーの低下に直面する中、より本質的な価値創造(ポートフォリオ企業のパフォーマンス向上など)に投資する必要がある。
- 資金調達環境の再構築: 新たな資金供給源として、個人投資家やソブリン・ウェルス・ファンドとの連携を強化し、従来の方法に頼らない資金調達戦略が求められる。
- 規模の経済: 市場での競争に勝つためには、規模の大きさを活かした資源配分やシナジー創出が重要になる。
日本の投資家や経営者にとっても、これらの変化は直接的な関心事です。従来の「短期的なディール獲得」戦略から、「長期的かつ包括的な成長戦略」へのシフトは、今後のグローバル市場においても成功するための必須条件と言えるでしょう。
まとめ
この記事は、プライベート・エクイティ業界がこれまでの慣習から脱却し、変化する経済環境や資金調達の競争の中で、より戦略的で持続可能なアプローチを採る必要性を説いています。日本を含む世界各国の投資家にとって、これらの洞察は、今後の投資戦略や企業運営における重要な示唆となるでしょう。
以上が、Bainの「This Time It’s Different: The Strategic Imperative in Private Equity」記事の日本語訳と解説です。各セクションごとに、原文の意図と今後の業界動向、そしてそれが日本市場にどのような意味を持つかについて説明しました。


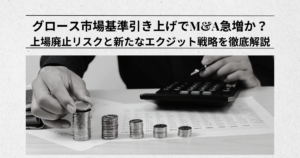

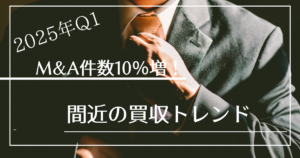





コメント