なぜM&A仲介会社からのしつこい営業が増えるのか
日本の中小企業を取り巻く経営環境は、少子高齢化や後継者不足などの影響によって大きな転機を迎えています。事業を継続するための選択肢が限られるなかで、M&A(企業の合併・買収)は「事業承継問題を解決する有力な手段」としていっそう脚光を浴びています。経済産業省中小企業庁も、ガイドラインや補助金・支援策を通じてM&Aを後押ししており、その結果として日本国内のM&A市場は急速に拡大しました。
一方で、M&Aをサポートする仲介会社の数も増え、IT化やオンライン化の進展に伴い、電話・メール・DM(ダイレクトメール)を駆使した営業アプローチが活発化しています。その中には、「しつこい営業」や「迷惑電話・DM」と見なされるものも珍しくありません。実際、多くの中小企業経営者や管理部門からは「何度断っても担当者が代わって再連絡が来る」「不動産の飛び込み営業のようにしつこい」「DMの大量送付で通常業務に支障が出る」といった苦情が多く寄せられています。
本稿では、こうした迷惑営業が増加する背景にある業界構造やインセンティブの問題点を探ります。また、公的機関や業界団体が進める規制強化の動向を踏まえ、実務レベルで企業が取り得る具体的な対処法を提示します。さらに、「どのような仲介会社を選べばよいのか」「信頼できるパートナーを見極めるポイントは何か」についても解説し、企業が安心してM&Aを検討するための視点をご紹介します。
1.中小企業M&A市場の拡大と新規参入の急増
日本の中小企業では、後継者不在のまま経営を続けざるを得ないケースが急増しており、経済産業省中小企業庁はM&Aによる円滑な事業承継を強く推奨しています。さらに、国内外の投資家や事業会社の買収意欲の高まりもあって、中小企業向けのM&A市場は拡大の一途をたどっています。
こうした需要増に応じて、M&A仲介会社の参入ハードルが下がり、新規事業者が相次いで誕生しました。これまで大手監査法人系や金融機関系のコンサルファームが中心だった市場に、独立系や地場密着型などの小規模仲介会社までが多数参入し、業界全体が激しい競争にさらされるようになったのです。その結果、案件獲得のための過剰な争奪戦が生まれることになりました。
2.激化する競争と「売り手・買い手」奪い合いのプレッシャー
M&Aでは「良質な売り手企業」や「投資余力・シナジーを期待できる買い手企業」が限られるため、一つの案件に複数の仲介会社が群がる傾向にあります。成約1件の成功報酬が大きな収益源となることから、少しでも可能性があればスピード重視の提案を積極的に行い、「ウチに任せてほしい」という熱心な売り込みが加速しているのです。
特に新興仲介会社や営業力を前面に掲げる上場仲介会社は、株主や投資家に好業績を示す必要があり、四半期や期末などの節目で成約数を伸ばすことが強く求められます。こうした背景から、経営者の事情を顧みず「電話攻勢」や「DMの大量送付」に踏み切る事例も少なくありません。
3.上場仲介会社特有のノルマ構造と歩合制度
近年、「M&A仲介専門会社」の上場が続いており、上場企業となった仲介会社は決算ごとに売上や利益を拡大し、株主に成長性を示す必要があります。さらに、多くの営業担当者は高額な成功報酬が見込める歩合制で働いており、成約を取るごとに収入が大幅アップする仕組みです。
そのため、経営者が明確に拒否しても「1%でも可能性が残る限り、再度アプローチする」というマインドが働きがちです。結果的に「しつこい営業」として表面化し、企業側から見れば迷惑行為として受け取られてしまうのです。
4.営業担当者の実態:プレッシャーと行動原理
(1)過剰アプローチを生む強いノルマ
M&Aは1件あたりの成功報酬が高額ですが、成約率自体は決して高くありません。そのため「とにかく数多く当たって見込み数を増やす」という営業方針を取りやすく、担当者に課されるノルマも厳しくなりがちです。少しでも“拒否の余地”が曖昧であれば再度連絡を入れるなど、企業の都合を顧みない連続アプローチが行われることも多く見受けられます。
(2)過重労働と精神的ストレス
とりわけ新規参入や小規模の仲介会社では、営業担当者が膨大なリストにひたすらテレアポをかけたり、大量のDMを発送したりするため、過重労働と精神的ストレスに苦しむ事例が後を絶ちません。追いつめられた担当者が合理的判断を欠き、「迷惑と分かっていても連絡し続ける」という悪循環に陥るケースも存在します。
5.公的機関による注意喚起と規制強化の動向
・中小企業庁のガイドラインと登録制度
中小企業庁では、M&A支援機関登録制度の運用に加え、仲介会社の業務内容や営業手法について適切性を確保するためのガイドラインを策定しています。両手仲介(売り手と買い手を同時に仲介する手法)の場合は利益相反が起きないようにすることや、料金体系の明示などが求められています。
迷惑電話やDMについても、明確に拒絶されているにもかかわらず営業を継続するような悪質行為には、登録取り消しや補助金・助成金対象外とする可能性を示唆しており、一定の抑止力を働かせようとしています。
・業界団体による自主的取り組み
一般社団法人M&A仲介協会(MAIA)や日本M&A協会などの業界団体は、会員企業に対して倫理規定や行動ガイドラインを示し、苦情対応窓口を整備しています。こうした団体に加盟している仲介会社は、コンプライアンスの意識や専門的知識をある程度備えている可能性が高いといえます。
業界全体の評判が悪化すれば自社にも影響が及ぶため、自主ルールや資格認定制度の整備を通じて「自浄作用」を機能させようとする動きが強まっています。
・今後予想される法的規制の強化
しつこい営業活動は、不動産や保険の分野でも社会問題化してきました。日本では特定電子メール法や個人情報保護法によって一部の営業行為が規制されていますが、企業情報や株式譲渡など特殊な領域を扱うM&A仲介では、さらに踏み込んだ法整備を求める声が大きくなっています。
今後はM&A支援機関登録制度の厳格化や行政処分に関する明確なルール設定などが進む見込みで、追加的な法的規制が行われる可能性も十分に考えられます。
6.実務的な対処策:迷惑営業から自社を守るには
①明確な拒否の意思表示
基本かつ最重要の対策は「はっきり断る」ことです。
- 「現在M&Aは検討していないので連絡は不要です」
- 「他社と契約済みなので、今後の連絡はお断りします」
といった具合に、曖昧な言い方を避けて明確に伝えましょう。「時期がきたら連絡してほしい」などと言うと、“時期がくればチャンスがある”と解釈され、再アプローチされやすくなります。遠回しではなく、きっぱり断る姿勢が大切です。
②対応窓口の一本化と社内ルール
営業電話やDMへの社内対応を一本化し、他部署や社員に回さないルールを設けると混乱を防ぎやすくなります。
- 専用アドレスや問い合わせフォームの設置
総務部門など特定担当者のみがチェックできる窓口を開設し、不要な部署へは回さない工夫を。 - 電話対応マニュアルの整備
全社員に「M&A営業の電話はまず○○部署へ回す」と周知しておくことで、現場の負担を軽減します。ITツールで営業メールを自動仕分けするなど、テクノロジーを活用するのも有効です。
③法的措置の検討と警告
度を越えた迷惑営業や、代表番号以外の私的な連絡先への繰り返し電話など悪質なケースでは、法的手段も選択肢に入ります。
- 警告文の送付
内容証明郵便で「これ以上営業行為を続ければ法的措置をとる」と書面で通知すると、仲介会社側にリスクを自覚させられます。 - 弁護士への相談
個人情報保護法違反の疑いがある場合や悪質性が高い場合は、弁護士による交渉・対応を検討してください。
④公的窓口・業界団体への通報
中小企業庁「不適切な支援行為に関する情報提供」問題行為を報告することで、行政指導や登録取り消しの可能性があり得ます。
一般社団法人M&A仲介協会(MAIA)苦情対応窓口加盟仲介会社に対する苦情受付や調停機能を有しています。明らかに不適切な営業を受けた場合は、こうした団体を通じて改善を促すことを検討しましょう。
苦情相談窓口|一般社団法人 M&A支援機関協会(MAAA)一般社団法人 M&A支援機関協会は、日本国経済の発展と維持に寄与することを目的とし業界全体のレベルアップを通じて公www.maa-a.or.jp
7.迷惑DMの最新動向とテクノロジー対応
・特定電子メール法・個人情報保護法の強化
日本では特定電子メール法によって原則「オプトイン(事前同意)」が必要とされるケースがあるほか、受信拒否(オプトアウト)を明確に認める規定があります。これを無視して送信を続ければ行政指導や罰則の対象になり得ます。また、経営者個人のメールアドレスへDMを送る場合、個人情報保護法の観点からも問題となるリスクがあるため、送信側には注意が求められます。
・セキュリティソフトや迷惑メールフィルタの活用
ほとんどのメールサーバーやセキュリティソフトにはスパムフィルタが備わっており、送信ドメインや本文の特徴を判別して自動的に迷惑フォルダに振り分けることが可能です。適切な設定をすれば、DMによる被害を大幅に軽減できます。
・企業情報開示の制限と問い合わせフォームの利用
ウェブサイトやパンフレットに代表電話や代表メールアドレスを記載していると、営業リストに載りやすくなります。近年はサイト上でメールアドレスを画像化したり、問い合わせフォームを設置したりして迷惑メールを減らす企業が増えています。問い合わせ時に簡易的な本人確認を行うだけでも、不要な営業連絡をある程度抑制できます。
8.信頼できるM&A仲介会社を見極めるために
迷惑営業が横行する一方で、誠実かつ専門知識を備えた仲介会社も数多く存在します。以下の観点を踏まえ、信頼できるパートナーを選択することが重要です。
【1】公的な登録・認定制度の確認
- 中小企業庁のM&A支援機関登録制度
登録要件を満たしている仲介会社は、コンプライアンス体制や専門性について一定の基準をクリアしていると見なせます。
【2】過去実績や評判のリサーチ
- 成約事例の開示
過去に扱った案件の規模や業種が自社と近いか、どのような成果を出しているかを確認します。 - 口コミ・専門家からの評価
公認会計士・弁護士・中小企業診断士など第三者の専門家が、その仲介会社をどう評価しているかも参考になります。広告文句だけをうのみにせず、実際の利用企業が満足しているかを複数の情報源で確認しましょう。
【3】コミュニケーション力とヒアリング重視の姿勢
M&Aは企業の将来を左右する重大な意思決定です。経営者の想いやビジョンを丁寧に聞き取り、最適なスキームを考えて提案する仲介会社であるか否かは非常に重要です。成約のみをゴールとし、押し売り的に話を進める担当者が目立つ場合は注意が必要です。逆に、経営者の価値観を尊重し、リスクや課題を正直に指摘してくれる仲介会社は信頼に値するといえます。
9.まとめと展望
日本の中小企業向けM&A市場は、後継者不足や成長戦略の必要性から拡大を続け、今後も多くの企業にとって重要な選択肢となるでしょう。一方で、M&A仲介会社も乱立しており、過当競争の余波として「しつこい電話営業」や「大量DM」などの迷惑行為が後を絶ちません。公的機関や業界団体は規制強化や自主ルールの整備を進めていますが、抜本的な改善には時間がかかるのが実情です。
企業側が実務的にできる対策としては、まず迷惑営業をはっきり拒否すること、社内の窓口を一本化すること、ITツールを活用すること、さらに必要に応じて弁護士や公的機関へ相談・通報するといった具体策が挙げられます。また、仲介会社を選ぶ際は、公的登録や実績、評判、料金体系の透明性などを多角的に確認し、慎重に判断することが大切です。M&Aは企業の未来を左右する意思決定であり、誤った相手に依頼すると、高額な手数料を払うだけで望む結果が得られないリスクもあります。
理想的には、仲介業界全体の質が向上するとともに、企業側のリテラシーも高まって「健全かつ円滑なM&A」が増えていくことが望まれます。現在、貴社でM&Aを検討中、またはしつこい営業にお困りの場合は、公的登録された仲介会社や信頼できる専門家へご相談ください。当社では弁護士・公認会計士・税理士など各種専門家と連携し、経営者の思いと企業価値を最大限に尊重したM&Aアドバイザリーをご提供しています。初回のご相談や情報交換はお気軽にお問い合わせください。
M&Aは、企業の未来を大きく拓く鍵となり得ます。しかし、その鍵を託すパートナーを誤ると、企業や従業員の将来を危うくしかねません。今回の記事を参考に、正しい情報と知識を身につけ、安心してM&Aを活用していただければ幸いです。
プライマリーアドバイザリー株式会社
代表取締役 内野 哲
プライマリーアドバイザリー株式会社経済産業省中小企業庁 M&A支援機関登録制度・M&A仲介・M&Aアドバイザリーのプライマリーアドバwww.primary.co.jp
本稿は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の法律相談・税務相談に代わるものではありません。実際の検討にあたっては、必ず弁護士や公認会計士・税理士などの専門家にご相談ください。



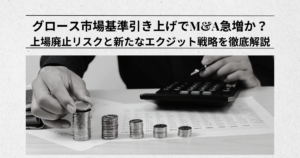

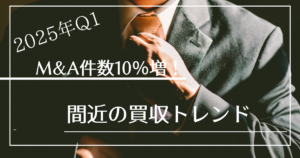




コメント