1.「純資産」とは何か?
1-1.貸借対照表から読み解く企業の真の価値
貸借対照表(バランスシート)は大きく「資産」「負債」「純資産」の3項目で構成されます。
- 資産(総資産):会社が保有する現金・預金・売掛金・在庫・不動産・設備・権利などの経済的価値
- 負債:借入金・買掛金・未払費用など、会社が将来的に支払う義務
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余の価値
つまり純資産は「会社が実質的に保有している価値」であり、日本の会計制度では「資本金」「資本剰余金」「利益剰余金」「その他包括利益累計額」などを含みます。過去の利益の積み上げや資本の厚みによって、企業がどれだけ安定した財務基盤を築いているかを測るうえで欠かせない指標です。
1-2.なぜ純資産が重要なのか
経営判断や株主への報告では、単年度の「当期純利益」や「営業利益」が注目されがちです。一方で、創業期からの累積データをすべて反映し、現時点での企業の総合力を示すのが純資産です。
- 純資産がプラスかマイナスかで、企業の安全性・健全性は大きく変わる
- 配当原資や設備投資の源泉となり、成長余力を左右する
- 利益を継続的に積み上げてきた企業ほど、財務面で高い評価を受けやすい
とりわけ株式譲渡を伴うM&Aでは、買い手は企業がもつ純資産の内容を細かく点検し、今後の投資リスクや投資回収プランを検討します。売り手としては、純資産をいかに健全かつ大きく保つかが、成功裡のM&Aや高い株価算定につながるカギとなるのです。
2.M&A価格のベースとなる「時価ベースの純資産」
2-1.簿価と時価の違い
非上場の中小企業では、不動産や設備を取得時の「簿価」で計上し続けているケースが少なくありません。しかしM&Aにおける企業価値評価では、原則として「時価評価」が行われます。
- 簿価:会計上の帳簿価格や減価償却後の残高など
- 時価:現在の市場における客観的な取引相場(実勢価格)
例えば、創業時に1,000万円で購入した土地が現在2,000万円の市場価値をもつ場合、貸借対照表には1,000万円の取得価額がそのまま残っていることが多いでしょう。しかしM&A交渉では、買い手は「この土地に2,000万円の価値がある」と評価するのが通常です。
2-2.時価ベースの純資産がM&A価格の基準になる
M&Aの株式価値(譲渡価格)は、まず「時価ベースの純資産」を算定するところから始まることが一般的です。
- 資産(不動産・車両・設備・保険など)を時価で再評価
- 負債(借入金・買掛金・引当金など)を正確に精査
- その差額(時価純資産)を洗い出す
これにより、企業のリアルな財務体質を把握します。中小企業のM&Aでは、交渉段階で初めて不動産や設備を見直した結果、簿外債務が発覚したり、貸借対照表の勘定科目が曖昧だったりして想定外の修正が生じるケースもしばしばです。したがって、専門家(公認会計士・税理士など)と早期に棚卸しを行うことが望まれます。
3.「時価純資産+営業権」で決まるM&A価格の基本構造
3-1.株式価値 = 時価純資産 + 営業権(のれん)
M&Aで買い手が取得するのは「会社(株式)」です。その評価額は大きく二つに分解できます。
①時価純資産:再評価した資産・負債の差額
②営業権(のれん):ブランド力、顧客基盤、独自技術、ノウハウなど帳簿には載りにくい無形の価値
たとえば純資産が1億円あっても、将来性が乏しければ営業権はほとんど評価されない場合があります。一方、純資産が1億円でも顧客基盤や独自技術に優位性があれば「のれん」が数千万円〜数億円上乗せされることがあるのです。
3-2.営業権の相場感:中小企業の場合
中小企業M&Aでは、営業権(のれん)を「実態営業利益の1〜3年分」とざっくり見積もる手法がよく用いられます(あくまで一例で、業種・事業特性・シナジー効果により調整します)。
- のれんが高く評価されやすいケース
- 独自のAI技術や特許技術などを持ち、成長性が高いIT・テック企業
- 大量のロイヤル顧客や会員データがあり、競合優位性が明確なサービス企業
- 市場で独占・寡占状態にあり、模倣が困難なビジネスモデルを保有する企業
一方、コモディティ化しやすい事業の場合(卸売業や飲食店など)は、「他社でも同様のビジネスが可能」と買い手が判断しがちなため、のれんがつきにくい傾向があります。
4.実際のM&A市場での価格決定ポイント
4-1.買い手はプロフェッショナルであることが多い
M&Aに参画する買い手企業は、金融機関やファンド出身者が担当していたり、複数回の買収経験をもつケースが一般的です。そのため、売り手が「高い価値がある」と主張しても、客観的根拠に乏しければ受け入れられにくいのが実情です。
- 無形資産(のれん)の評価は厳格に行われる
- 過大評価すると買い手側の“のれん償却”負担が大きくなり、敬遠される
- 買い手は複数の候補企業を比較検討しており、価格が過度に高い案件は即座に見送られる可能性もある
4-2.営業権の償却リスク
日本基準(税務上)では、買収後の「のれん」は原則5年で償却(費用化)されます(会計上は最長20年以内で定額償却することも認められています)。のれんを大きく積み上げるほど、買い手は毎年の経費負担や減損リスクが高まるのです。
- のれん償却費が大きいと買い手の利益圧迫につながる
- 期待したシナジーが得られなければ、のれん減損処理のリスクも高まる
こうした要因から、買い手はのれん評価に慎重にならざるを得ません。
5.中小企業M&Aにおける価格の一般的な目安
5-1.「純資産+実態営業利益×年数」というフレームワーク
多くの中小企業M&Aでは、次のように算定するケースが多いといわれています。
譲渡価格 = 純資産 + (実態営業利益 × 1〜5年程度)
ここでいう「実態営業利益」とは、オーナー経営者が一般水準より高額な役員報酬を得ている場合に補正したり、私的経費を排除したりした“本来の事業利益”です。
- 年数が1年分程度:成長性が低く、安定性も乏しい事業
- 年数が2〜3年分:一定の収益性・安定性が見込まれる事業
- 年数が4〜5年分:成長余力が大きい、あるいはシナジー効果が期待できる事業
この「年数」はあくまで目安であり、企業規模や業態、買い手との相性によって変動します。
5-2.純資産を高める経営のメリット
純資産はM&A価格の“土台”となるだけでなく、銀行融資や外部投資家との協議においても信用力を高めます。その結果、日常の資金調達にも好影響を与え、経営の安定につながるという利点があります。
6.純資産を高めるための経営上のポイント
「将来のM&Aで高く評価されたい」「事業承継をスムーズに進めたい」という経営者の方は、以下のような施策を検討するとよいでしょう。
- 内部留保の充実
- 利益をしっかり残すために配当や役員報酬のバランスを見直す
- 一時的な利益ではなく、継続的に稼げる体質を目指す
- 不要資産や不採算部門の整理
- 遊休不動産や過剰在庫、収益を圧迫している部門を見直す
- 不要な負債を圧縮し、バランスシートを健全化する
- 時価評価を念頭に置く
- 定期的に不動産や株式などの市場価格を把握し、経営判断に活かす
- M&Aの際に客観的な評価額をスムーズに提示できるようにする
- 投資家や金融機関との関係強化
- 必要に応じて増資や資本提携を検討し、自己資本比率を向上
- 事業計画を外部に丁寧に説明し、信用力を高める
いずれも短期的な利益のみを追うのではなく、長期的・安定的な企業価値の向上を目指す視点が重要です。
7.よくある誤解と注意点
7-1.純資産が高い=必ずしも高値がつくわけではない
純資産はM&Aのベースにはなるものの、以下のような場合には評価が伸び悩むこともあります。
- 遊休資産の比率が高く、本業の収益力が乏しい
- オーナーが会社資産を私的に流用していた履歴があり、実質的には活用しづらい
- 買い手にとってシナジーが見込めず、のれんを上乗せしづらい
こうしたケースでは、純資産が大きくても譲渡価格が純資産を下回る場合があるため注意が必要です。
7-2.売り手の思いだけで「のれん」は上がらない
のれんは買い手が見込む将来の収益力やシナジーに基づいて算定されるため、売り手の希望だけで値上がりするわけではありません。
- 「老舗ブランドだから」「地域密着で知名度があるから」という主観的評価があっても、客観的根拠がない場合はのれんに反映しにくい
- のれんが大きいほど買い手の償却負担も増えるため、過度な上乗せは難しい
7-3.IT・テック系企業など成長株の例外
ITやテック系ベンチャーなど、極端に成長が見込まれる事業では、純資産に対して数倍以上ののれんがつくことも珍しくありません。ただし、その分期待どおり成長しなかった場合のリスク(のれん減損等)も大きく、買い手は厳重にシナジーや将来性を検証します。
8.M&A交渉をスムーズに進めるためのポイント
8-1.客観的な評価レポートの準備
- 不動産や設備、在庫などの価値を第三者機関に評価してもらい、根拠のある時価を把握する
- 簿外債務やリース契約、連帯保証などの有無を税理士や公認会計士とともに早期に洗い出す
- 買い手のデューデリジェンス(DD)に備え、必要書類や資料を整理しておく
8-2.将来計画・ビジョンを明確に提示
- 「どのように企業を成長させ、利益を生み出すのか」を数値を交えて示す
- 数年間の事業計画を作成し、買い手がのれんに納得できる根拠とする
- 経営者やキーマンの退任リスク、後継者の育成計画なども明確に伝える
8-3.専門家の活用と第三者の意見
- M&Aアドバイザー、弁護士、公認会計士・税理士を早めにチーム化し、連携を強化
- 企業価値算定や法務リスク洗い出し、税務対策から契約交渉までトータルでサポートを得る
- 専門家同士の情報共有が進むほど買い手との信頼関係も構築しやすい
8-4.買い手候補を幅広く探す
- 単独の買い手だけに限定せず、複数の候補と並行して交渉し、公正な市場価格を把握する
- 事業内容や業種との相乗効果が高い買い手を見つけられれば、高いのれんを提示してもらえる可能性がある
9.まとめ:純資産を常に意識し、将来のM&Aに備えよう
ここまで解説したように、中小企業M&Aでは「純資産」と「のれん(営業権)」を組み合わせて株式価値が決定されることが多く、一般的には
譲渡価格 = 純資産 + (実態営業利益 × 1〜5年分)
というフレームワークが活用されています。
- 純資産:バランスシート上の実質的な会社の価値(時価評価が大前提)
- のれん(営業権):将来の収益力やブランド力、シナジーを反映する無形の価値
- 価格交渉:売り手は高値、買い手は合理的な値段を求めるため、説得力のある根拠が必要
「いつかは事業承継やM&Aを」と考えている経営者の方は、早期から純資産を厚くして財務体質を改善するとともに、将来の成長ストーリーを明確にしておくことが肝要です。
M&Aには法務・税務・財務・人事・PMIなど幅広い専門知識が求められる
M&Aのプロセスは複雑になりがちですので、下記のような専門家の力を借りることでディール成立を円滑に進め、企業価値を最大化できる可能性が高まります。
- 弁護士:契約書や法務リスクの管理、利害調整
- 公認会計士・税理士:財務・税務デューデリジェンス、最適な税務スキームの立案
- M&Aアドバイザー:企業価値算定や買い手探索、交渉サポート
【ご相談はお気軽にどうぞ】
本稿では「純資産」と「のれん(営業権)」の基本的な位置づけと価格算定の一般的な手法を整理しました。ただし、実際のM&Aは企業ごとに事情が異なり、財務・法務・税務・経営者個人の相続対策など包括的な検討が不可欠です。
当事務所では、M&Aアドバイザリーの経験を活かして、
- 中小企業の価値最大化
- スムーズな事業承継
- 買収交渉・PMI(統合プロセス)のサポート
などを一括してご支援しております。M&Aに関するご不明点やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門家チームが丁寧にヒアリングを行い、最適なソリューションをご提案いたします。
プライマリーアドバイザリー株式会社
代表取締役 内野 哲
プライマリーアドバイザリー株式会社経済産業省中小企業庁 M&A支援機関登録制度・M&A仲介・M&Aアドバイザリーのプライマリーアドバwww.primary.co.jp
本稿は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の法律相談・税務相談に代わるものではありません。実際の検討にあたっては、必ず弁護士や公認会計士・税理士などの専門家にご相談ください。


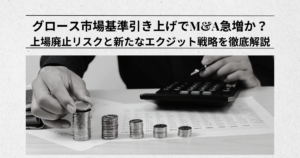

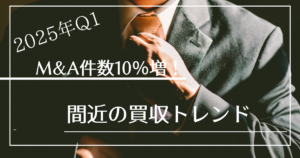





コメント